セルフ1とセルフ2(1/3)
コーチングのルーツを見てみると
やはり、スポーツにあります
例えば・・・
監督と言えば、スポーツチームの
監督や映画制作の監督のイメージ
がありますよね
コーチと呼ぶのは、スポーツチーム
の指導者しか思いつかないのは、
偶然なのでしょうか・・・?
それはさておき、コーチングの
ルーツの一つがスポーツでした
そして・・・
僕に影響を与えているティモシー
・ギャロウェイさんもテニスの
講師などをしていたようですが
1976年にインナーゲームと言う
著書を日本でも出版しています
20年以上経った2000年に改訂版
が紹介されているようですが、
ティモシーさんは独特の視点から
1970年代ではありえない発想で
スポーツ界に旋風を巻き起こした
のでした
ココで少し、その
考え方を説明します
前提として・・・、
一人の人間の中には
二人の自分がいます
このように考えました
一人は、
本能的に知っているプレー
をしようとする自分です
(セルフ2と表現しています)
もう一人は、
命令を出し、評価し、もっと
上手くやらせようと叱咤する
自分です
(セルフ1と表現しています)
ちなみにですが・・・、
叱咤(しった)とは大声を張
り上げてしかりつける事です
無心に取り組む自分を
セルフ2と言い・・・
冷たい目で眺めて・・・
「そんな事じゃダメだ
もっと上手くやれ 」
とセルフ1がささやきます
セルフ1の声が聞こえた途端に
セルフ2は緊張し本来セルフ2が
知っている最高のパフォーマンス
ができなくなってしまいます
セルフ1は監視役で口うるさいです
さらに、くどくて、指示や命令を
出してきます
さらにティモシーさんは
コーチについて次のよう
に言っています
コーチの仕事は、
対象者の心をセルフ1に支配させずに
セルフ2に自由にプレーをさせること
それこそが、潜在的な能力の発揮で
あってコーチの役割りである
ティモシー節、あっぱれです
僕も、ココには深く共感し
影響を受けています
世界中のスポーツ界において
努力と根性と熱血バリバリで
イケイケな、1970年代に
この視点で指導者として対象者を
見ていたのは、正に、時代の先を
行く考え方です
テニスの本として出版した
インナーゲームだったのですが
ティモシー旋風の幕開けです
テニスのコーチだけでなく
選手からも反響が良く・・・
テニスの選手だけでなく他の
スポーツ選手からも反響が良く
さらに、スポーツ界だけでなく
1980年代後半のアメリカでは
ビジネス界からも注目を集めます
ビジネスコーチングとして
時代を切り開いていったのです
そもそも、
当時のアメリカは・・・
経済不況と規制緩和をはじめとした
生活環境や生活スタイルの変化から
顧客のニーズの変化のスピードが
増した事で社員の自立が急速に
求められたのでした
上司の命令を待って動くだけでは
末端の対応スピードには追いつか
なかったようです
自立した社員は上司に報告はする
ものの社員が個々でそれぞれが
考えて対応する必要性に
迫られている分けですから
従来の、「支配と従属」の関係
ではなく、コーチングが適応し
ていったのです
そして・・・
日本でも、1990年代後半以降に
なると、長引く不景気の影響から
多くの企業で組織のフラット化が
進み、中間管理職が間引きされて
ビジネスコーチングが求められました
しかし・・・
中々、日本では、コーチングを
実用化するには浸透しきれない
なかで・・・
コーチングを活かした企業と
無視した企業で企業体質に
差が出ていたのが、おそらく、
現状だったのでしょうが、
結局は、コーチングとは、
人間力を向上させてくれる
分けですから、会社の業績
はもちろんですが・・・
社内の雰囲気や人間関係や
メリハリあるライフスタイル
などなど、あらゆる所で飛躍
し向上していくのでしょう
菅原さんは次のように
印象深くまとめています
- 人は潜在能力を備えた存在であり
できる存在である - 人はよりよい仕事をすることを
望んでいる
このような事を会社の上司が
心の底から望んでくれたら
良いのでしょうが・・・
多くの日本人はこのような心の
在り方に到達できる程、自分の
人生を満たしていません
とはいえ、
相手を認めて、信用し、
可能性と潜在能力をフルに
活かす事は真実だと思います
そして・・・
よりよい仕事を望んでいる事を
認めて、考慮する事が人間の
幸福追求の一つであることも
真実だと思います
僕もココには凄く共感しています
(2/3へ続きます)
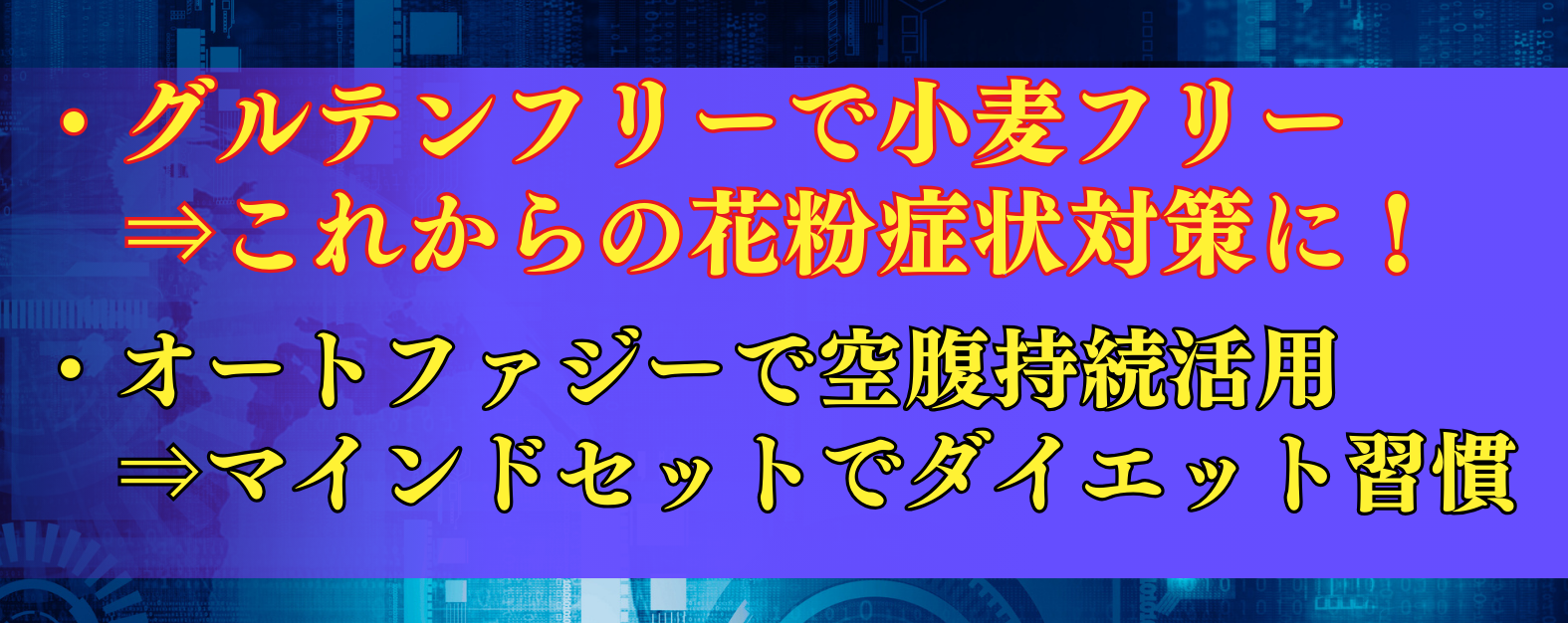
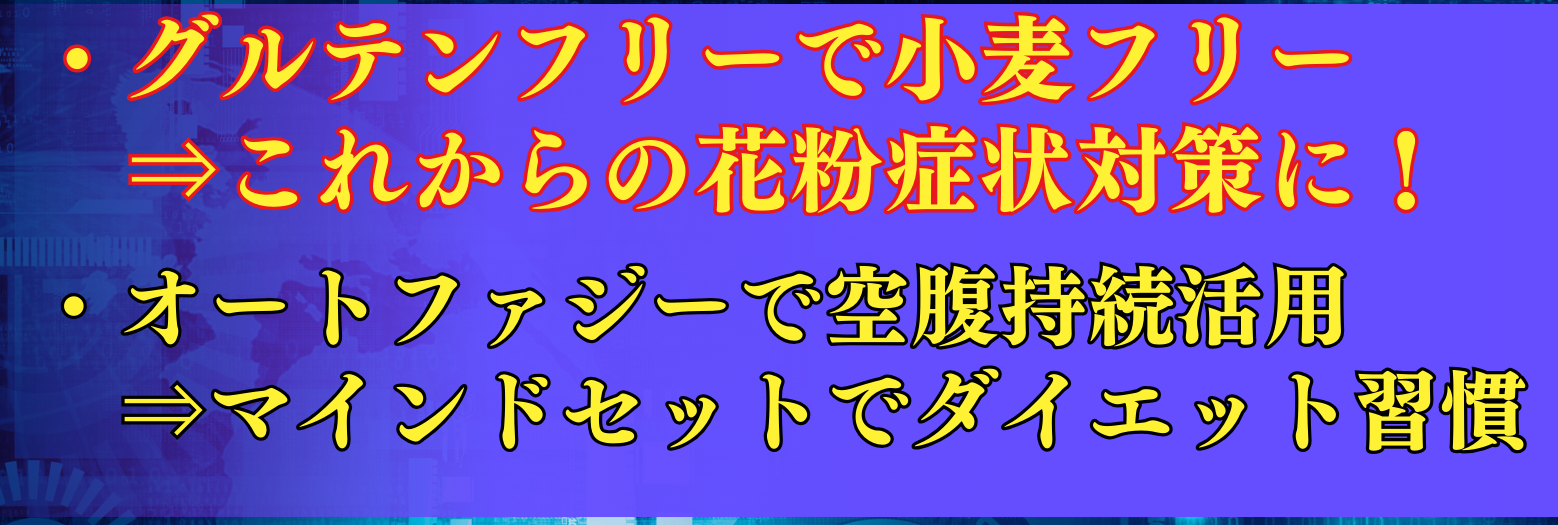
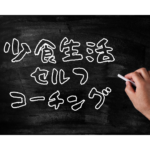
コメント