セルフ1とセルフ2
(2/3)
しかし、
よくよく考えて見ると
そもそも・・・
3年先に入社した会社の先輩は
後から入った社員の成長を内心、
警戒しながら一緒に仕事します
係長は課長の顔色を見ています
課長は部長の顔色を見ています
部長は専務や常務の役員の
顔色を見ているでしょう
心理としては・・・
- 自分が下に見られたくない
- 競争に勝ちたくて負けたく
ない - バカにされたくない
- 優位に立ちたい
- 抜かされたくないし
できれば追い抜きたい
このような湧き上がる感情は、
幼少期からの長い年月による経験
や体験によってできたものです
簡単には変えられません
親の教育方針や学校教育や
集団行動や集団生活での
上下関係の影響です
部活動などでは、先輩は絶対で
一発芸をさせられたり、パシリ
になったりで練習はそっちのけ、
ボール広いを一日中したりする
こともあったりする分けです
それでも、かわいがってもらっ
たりして、いざこざなどが起き
たとしても困った時は、
守ってくれたりする事もあります
決して、悪い事
ばかりではありません
10代の時は、一年一年の成長の
差は大きいですのでそう簡単には
先輩を超えられないですし・・・
運動能力で超えたとしても、国の
教育システムは知識が先輩を超え
られないようになっている分けです
最近は、インターネットや塾など
がありますので個人の興味と成長
を引き上げてくれて違ってはきて
いるとは思いますが、それは最近
の事です
ですから・・・
縦社会は絶対で、後輩は先輩を
超えられないものであると言う
社会的なプログラミングが刷り
込まれています
先輩は後輩から超えられない
可能性は高いものであって、
もしも、超えられようものなら
自己評価が下がってしまい、
恥ずかしい出来事であると言う
社会的なプログラミング的思考
が刷り込まれています
このような相互関係から日本社会
は出世するにも気を使いますし、
そもそも、出世させないように
人事を組んだりしたりさえします
つまり・・・
自分の能力以下の人を自分の部下
においてしまって能力がある社員
にはチャンスを与えなかったりで
蹴落とす人事だったりします
これでは、企業も国も
全ての共同体は先細りです
だからこそ、国力が
弱ってしまいます
例えば・・・
令和の日本においては、ダントツ
に走っているランナーの揉め事で
はなくて・・・
第二集団、第三集団を走って
いるランナーが足を引っ張て
いるようなものですから
残念で、見ていられません
ですから、柔軟に対応できない
国や大企業は置いておいて、
個人ではこのような縦社会や支配
と従属の関係性からの刷り込みに
よる社会的なプログラミングからは
脱皮して自立ある生活が
急速に求められています
残念ですが、多くの日本人が
人生の途中で命を投げ出して
しまっている分けですから
その数は世界トップクラス
との事で悲しい事です
きっと・・・
自立した個人で世の中を溢れ
させないと過ごしやすい世の
中にはならないのでしょう
自立による共同体であって
共存や共生の社会です
そのように思っています
とにかく、ひがみやねたみが
多くて愚痴と文句と悪口を
生きがいにしている分けです
他人の幸せを喜べずに・・・
「他人の不幸は蜜の味」
などと言って・・・
「人生はお金だよ」
「お金が全てだ」
などと言って・・・
もはや、狂っています
その狂った思考に脳内では
ドーパミンがどんどん出ていて
当の本人は、気持ちの良い
快楽に浸っています
とまぁ・・・、
「そんな人がいますよ」
と言う事ですが、きっと
そんな人も少なくないのです
今でも、世間では・・・
21世紀で2020年代になっている
令和時代の日本でもコーチングは
必要で、特にセルフコーチングに
期待して注目しています
仕事への活用はもちろんですが
安定した健康的な生活への動力
として「有り」だと思っています
なぜかと言いますと
前提として・・・
少食生活は、マインドセットが
できていないと無理だからです
仮に、出来たとしても苦労して
大変な思いの中での少食生活は
おすすめできません
ストレスなどで、逆に、
不健康になってしまうからです
マインドセットがどうしても
できない要因にはちゃんとした
理由が存在します
困った事にこの分野にもまるで
洗脳のような刷り込みが有るの
ですが、それは、教育や広告や
テレビやラジオや新聞などなど
いくらでもはびこっています
関わっていく人間関係でも影響
しますし、完全ブロックは無理です
(3/3へ続きます)
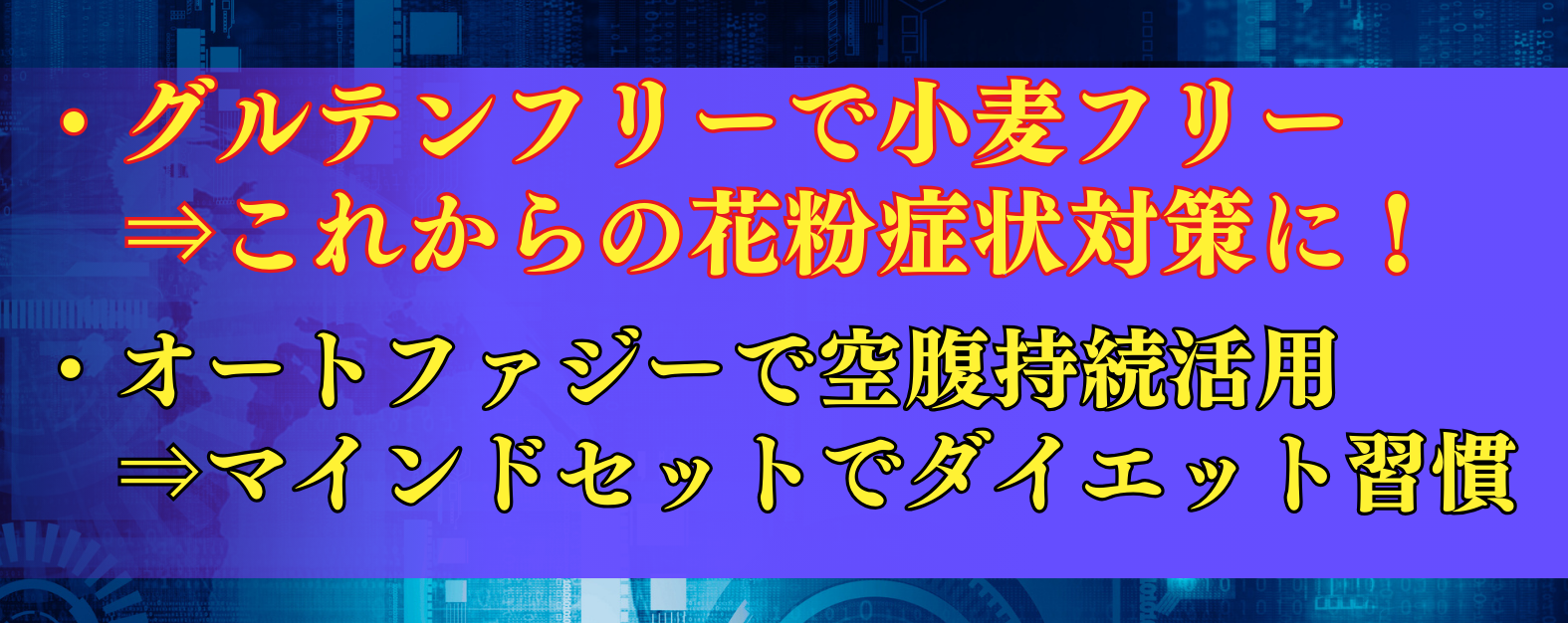
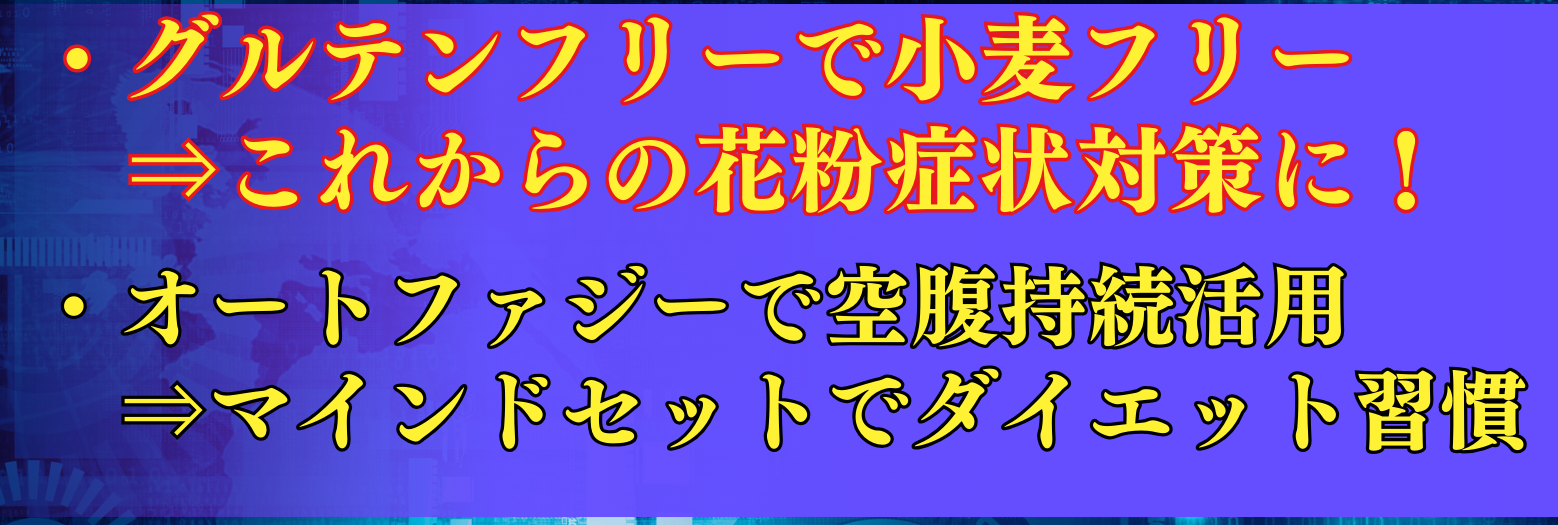
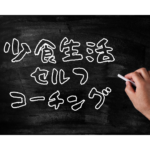
コメント